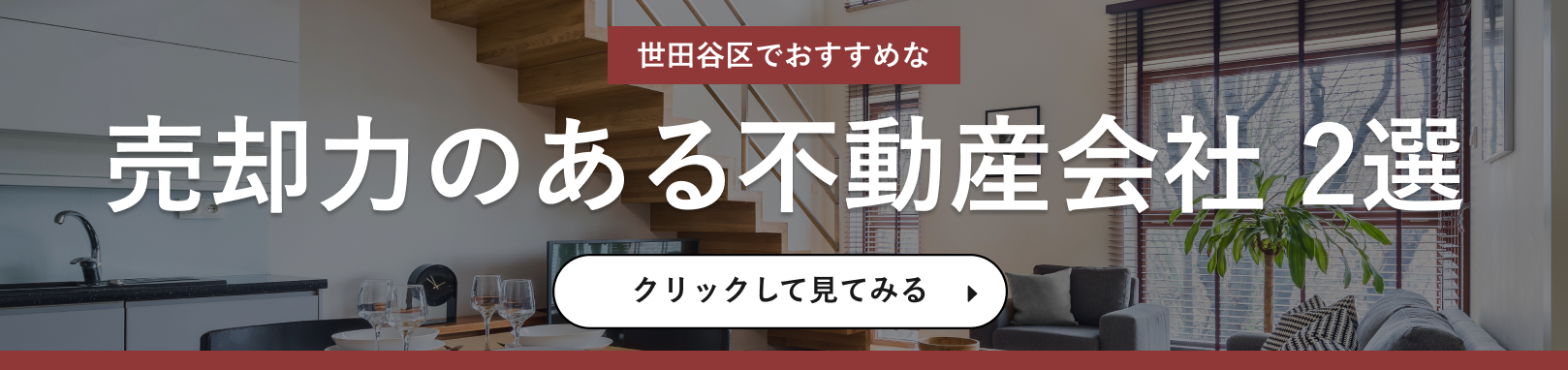「相続した不動産を売却したいけど、どんな売却方法があるのか分からない」
「どの書類が必要なのか分からない」
相続した不動産の売却を検討している方は、上記のような悩みや疑問を持っている方も多いでしょう。
相続した不動産は状況によって売却の流れや必要な書類が異なり、売却後に後悔してしまう恐れがあります。そのため、事前に流れや必要な書類、利用できる制度を知っておくことが重要です。
そこで、本記事では相続した不動産の売却に関して、流れや必要な書類、利用できる制度などについて解説していきます。売却する際の注意点も紹介しているので、相続した不動産の売却を検討している方は参考にしてみてください。
相続した不動産を売却する流れ

まずは、不動産を相続し、売却するまでの流れを紹介します。
- 1.遺言書の有無を確認
- 2.遺産や債務の確認
- 3.遺産分割協議
- 4.名義変更
- 5.相続税の申告と納付
- 6.不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 7.売買契約を結ぶ
- 8.引渡し
- 9.確定申告
不動産の相続手続きには期限があります。3カ月以内に遺言書の有無や遺産・債務の有無を確認し、相続するのか、放棄するのか決めければいけません。相続税の申告と納付は10カ月以内に行うことが必要です。
続いて、相続する際の各手続きについて解説していきます。
相続の各手続きの期限
相続に関する手続きの期限は以下の通りです。
| 手続き | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 財産も負債もすべて放棄する | 相続開始を知った日から3カ月以内 |
| 限定承認 | 財産も負債もすべて相続する | 相続開始を知った日から3カ月以内 |
| 準確定申告 | 被相続人の1月1日から高いしたまでの所得を確定申告する | 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 |
| 相続税の申告と納税 | 相続税を申告し、納付する | 相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内 |
| 遺産分割協議 | 相続人同士で遺産の分割方法を話し合う | 定めなし |
相続した不動産を売却するには、名義変更が必要です。原則、遺言書がある場合は、記載されている内容に従い名義変更を行います。
遺言書がない、かつ特定の相続人に引き継いでもらいたい時は、遺産分割協議を行います。この遺産分割協議には期限が定められていません。
不動産を売却し、相続税を納付する場合は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月までに現金化する必要があります。各手続きによって「相続開始を知った日から」「相続開始を知った日の翌日から」など条件が異なるので、気を付けましょう。
名義変更から売却までの流れ
遺言書や遺産分割協議を行い、相続人が決まったら、名義変更を行います。名義変更後から相続不動産の売却までの流れは以下の通りです。
- 1.名義変更
- 2.物件査定
- 3.媒介契約を結ぶ
- 4.売却活動スタート
- 5.売買契約を結ぶ
- 6.引渡し・残金決済
- 7.確定申告
相続した不動産の名義変更から引渡しまでは半年程度を見込んでおきましょう。買主がいつ現れるか分かりませんが、スムーズにいくと半年程度が目安です。
相続した不動産の名義変更に必要な書類

相続不動産の登記には、多くの書類が必要です。以下では、相続の状況別に必要な書類を紹介します。すべての状況に必要な書類は以下6つです。
- 登記申請書
- 相続関係説明図(任意)
- 相続に関する不動産の登記事項証明
- 被相続人の住民票(本籍地が記載されているもの)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 固定資産税評価証明書
状況によって必要な書類は以下の通りです。
| 状況 | 必要な書類 |
|---|---|
| 遺言書がある場合 | 【被相続人が作成】 ・遺言書 【市区町村役所】 ・不動産を取得する相続人の戸籍謄本 ・不動産を取得する相続人の住民票 |
| 法定相続分を相続する場合 | 【市区町村役所】 ・法定相続人の戸籍謄本 ・法定相続人の住民票 |
| 遺産分割協議のもと相続する場合 | 【申請者が作成】 ・遺産分割協議書 【市区町村役所】 ・法定相続人全員の印鑑証明書 ・法定相続人全員の戸籍謄本 ・不動産を取得する相続人の住民票 |
その他、必要な書類がある場合もあるので、相続が分かったタイミングで確認しておきましょう。
名義変更の方法
相続不動産の売却は売主を明確に示すために、名義変更が必要です。名義変更は2024年4月に義務化されています。これは、所有者不明土地問題を解決するためでもあります。
名義変更の方法は『法定相続』『遺言による相続』『遺産分割協議による分割』によって異なります。それぞれについては以下の通りです。
| 状況 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 法定相続 | 法定相続割合で共有のまま名義変更を行う | ・相続不動産を売却し、現金を相続人で公平に分けたい場合 |
| 遺言による相続 | ・遺言書がある場合に有効 ・遺言に従って名義変更を行う | ー |
| 遺産分割協議による相続 | 相続後に相続人同士で分割方法を決める話し合いを行う | ・遺言書がなく法定相続以外の方法で分割したい場合 ・遺言書がある場合に、遺言書とは異なる方法で分割したい場合 |
遺産分割協議は、相続人全員の同意を得ないと成立しないので、覚えておきましょう。
不動産売却に必要な書類

相続不動産を売却する際、売主は必要な書類を揃えておく必要があります。売却をスムーズにするためにも、早いうちに探しておきましょう。特に、境界線が明確でない場合は測量してから売却するため、早めの準備が必要です。
▼全ての不動産に必要な書類
- 登記簿謄本または登記事項証明書
- 売買契約書
- 物件購入時の重要事項説明書
- 登記済権利書または登記識別情報
- 固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
▼一戸建て、土地に必要な書類
- 土地測量図・境界確認書
▼マンション・一戸建てに必要な書類
- 物件の図面
- 設備の仕様書
- 耐震診断報告書
- アスベスト使用調査報告書
上記の書類以外にも、必要な書類が求められる場合もあるため、依頼する不動産会社が決まったら、事前に確認しておきましょう。
また、相続不動産を共有名義で売却する際は、相続者全員分の実印、印鑑証明書、本人確認書類が必要です。契約に立ち会えない人がいる場合は、委任状の作成が必要なので注意してください。
相続した不動産の売却で発生する費用と税金

相続した不動産の売却で発生する費用や税金には以下のようなものがあります。
| 費用や税金 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 売買契約書などの課税文書に課される税金 | 1,000円~6万円 ※契約金額によって異なる |
| 譲渡所得税 | 住民税と所得税をまとめたもの。不動産売却による利益に課税される | 【短期譲渡所得(所有期間が5年以下)】 売却価格×30% 【長期譲渡所得(5年超の所有期間)】 売却価格×15% |
| 消費税 | 仲介手数料などに課税 | 現行の税率 |
| 仲介手数料 | 不動産会社に報酬として支払う | 【400万円を超える場合】 売却価格×3%+6万円 |
| その他費用 | ・被相続人の戸籍謄本発行費用 ・相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書の発行 ・不動産登記事項証明書発行費用 ・固定資産税評価証明書発行 ・ハウスクリーニング費用 ・測量費 ・解体費用 ・税理士費用など | 被相続人の戸籍謄本発行費用:450円 相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書の発行:300~450円 不動産登記事項証明書発行費用:600円 固定資産税評価証明書発行:400円 ハウスクリーニング費用:3~10万円 測量費:50~80万円 解体費用:100~300万円 |
印紙税は、令和6年3月31日までに契約すると、軽減税率が適用されます。譲渡所得税に関しても、10年を超える不動産の場合は軽減税率が適用されるので、条件に当てはまる方は確認しておきましょう。
売却の状況によって必要な費用が異なるため、上記で紹介した全ての費用が発生する訳ではありません。どの費用や税金が発生するのか知りたい場合は、売却を依頼した不動産会社に聞きましょう。
相続した不動産の売却にかかる税金は相続人全員で支払う
相続した不動産の売却にかかる税金は、相続人全員で支払います。
財産を現金化し、分割する換価分割を行う場合は代表者が相続登記を行い、登録免許税や印紙税などを立て替えたうえで分割する際に相殺するのが一般的です。譲渡所得税に関しては各相続人が確定申告を行い、納付します。
相続不動産の売却が確定している際は、「いくらで売却できるのか」を知るために、売却価格の査定をしておくと良いでしょう。その際、査定依頼先は1社に絞るのではなく、3〜5つの複数社に同時に査定を依頼し、1番良い会社を選びましょう。
相続した不動産の売却で利用できる特別控除

相続した不動産を売却する際は、特別控除を利用できるケースがあります。上手く活用することで費用を抑えられるため、事前に利用できる特別控除や適用条件の確認が必要です。
| 特別控除 | 内容 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | 個人が居住用財産を売却し、一定の要件を満たした場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除される | ・居住している家屋、または家屋共に敷地や借地権を売却 ・家屋を解体した場合、売却まで居住以外に使用していない ・解体した日から1年以内に売却契約を結ぶ ・居住しなくなってから、3年目の12月末までに売却する ・売主と買主が親子や夫婦などの関係ではない ・売却した時に住宅ローン控除を受けていない |
| 相続空き家の3,000万円特別控除 | 被相続人が1人で住んでいた建物およびその敷地を相続により取得し、その空き家を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除される | ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋 ・マンションではない ・売却時の耐震基準に適合している ・相続開始直前まで被相続人が居住していた ・相続開始直前に被相続人以外で居住した者がいないこと ・これまで人に貸していないこと ・相続日から3年目の12月末日までに売却する ・平成28年4月1日から令和5年12月31日までに売却する ・売却価格が1億円以下 |
| 取得費加算の特例 | 家を相続した日から3年10カ月以内に譲渡した場合、譲渡所得税から一定の額を差し引ける特例 | ・相続または遺贈によって取得した ・相続時に相続税を納付している ・相続開始日の翌日から3年10カ月以内に売却 |
| 小規模住宅等の特例 | 面積が330㎡までの宅地を売却する際、条件に当てはまれば値の評価額を80%減額できる特例 | ・相続した子が相続の3年前までに自己所有の家屋に住んでいない ・被相続人(親)に配偶者や同居の親族がいない ・土地を相続税の申告期限までに所有している ・家を持たず、賃貸住宅に住んでいる子などが相続した |
上記以外にも自治体によって利用できる特別控除があります。売却を検討する際は、事前にどの控除が利用できるのか確認しておきましょう。
特別控除の詳細や適用条件は国や自治体のホームページに記載されています。見ても分からないという場合は、不動産会社に教えてもらいましょう。
併用できない特例に注意
相続不動産を売却する際、併用できるものとできないものがあるため、注意しましょう。

上記は、国税庁のホームページで記載されているものです。相続不動産を売却する際は目を通しておきましょう。
相続不動産の売却の失敗例

相続不動産の売却の失敗例は以下の3つが挙げられます。
それぞれの例を参考にして、相続不動産での失敗を未然に防ぎましょう。
親族と話し合わないで売りに出した
相続した不動産を親族と話し合わずに売却を進めたことで、トラブルに発展するケースがあります。売却に関する同意が得られていないまま手続きを進めると、後から異議を唱えられる可能性が高いです。
不動産は法定相続人全員の共有財産となるため、単独での売却は原則として認められていません。共有者の一部が反対した場合、売却手続き自体が無効となるケースが多いです。
さらに、感情的な対立が発生すると、親族関係に深刻な亀裂を生む恐れがあります。特に遺産分割協議が未了の段階で売却に動くと、協議のやり直しや法的トラブルにつながりかねません。
相続不動産の売却を円滑に進めるためには、親族全員と事前に話し合いをおこない、同意を得ることが不可欠です。また、遺産分割協議書の作成と、登記手続きの完了も必要です。
相場を調べずに依頼した
相続不動産の売却において、事前に相場を調べずに不動産会社へ依頼すると、大きな失敗につながる可能性が高いです。相場を知らないまま提示された価格に納得してしまうと、実際の市場価格よりも大幅に安く売却されるケースが少なくありません。
特に相続物件は売却を急ぐ傾向があり、焦りが判断を誤らせます。不動産会社によって査定額にばらつきがあるため、相場を把握していないと、適正価格かどうかの判断が困難です。
結果として、本来得られた利益を逃すリスクが高まります。適切な対応としては、複数の不動産会社から査定を取り、レインズや不動産ポータルサイトなどで近隣物件の価格を調査することが重要です。
売却後の税金を考えていなかった
相続した不動産を売却する際、事前に税金についての知識が不十分だと、思わぬ出費に直面する可能性があります。売却益が発生した場合、譲渡所得税が課されることがあるため注意が必要です。
譲渡所得は「売却価格-取得費-諸経費」で算出され、その金額に対して税率が適用されます。相続不動産では取得費が不明確になりやすく、売却益が大きく見積もられるケースもあります。
特に、被相続人が購入した時の資料が残っていない場合は、取得費を概算でしか計算できず、税額が高くなる可能性が高いです。結果として、売却後に想定外の税負担が発生し、手元に残る資金が大幅に減る事態も起こり得ます。
相続不動産の売却では、事前に税理士などの専門家に相談し、譲渡所得や特例の適用可否を確認することが重要です。
相続した不動産の売却が長引くとどうなる?

相続した不動産の売却が長引くと以下のような問題が発生する可能性があります。
それぞれの問題を把握して、相続した不動産の売却を長引かせないようにしましょう。
資産価値が下がる
相続した不動産の売却が長引くと、資産価値が下がるリスクがあります。主な理由は、建物の老朽化や管理状態の悪化です。特に空き家の場合は劣化が早く、買い手からの印象も悪くなりやすいです。
また、周辺の不動産市場の変動も影響します。地域によっては人口減少や地価下落により、時間の経過とともに売却価格が下がる傾向があります。早期の売却活動は、不動産の魅力を維持し、高値での売却を実現するうえで重要です。
資産価値を守るためには、迅速な判断と行動をしましょう。
メンテナンス費用や手間がかかる
相続した不動産の売却が長引くと、所有者には継続的なメンテナンス費用や管理の手間が発生します。空き家の状態が続けば、建物の老朽化が進み、定期的な清掃や修繕が必要です。
売却までの期間中に予想以上のコストがかかるでしょう。さらに、不動産を放置していると雑草や害虫の発生、近隣トラブルの原因にもなり得ます。対処するための労力や時間も無視できません。
遠方に住んでいる場合は、現地までの移動も負担です。また、維持管理が不十分な物件は見た目の印象が悪くなり、購入希望者から敬遠されやすいです。
結果として売却価格の低下や売却期間の長期化を招く可能性があります。相続した不動産は、可能な限り早期に売却を検討することで、無駄なコストと手間を最小限に抑えることが重要です。
固定資産税がかかる
相続した不動産を売却せずに保有し続けると、毎年固定資産税が課税されるため、売却が長引くほど負担が大きいです。固定資産税は土地や建物の評価額に応じて毎年1月1日時点の所有者に課される税金です。
仮に使用予定がない不動産を相続した場合でも、名義変更を済ませるとその瞬間から固定資産税の納税義務が発生します。売却を遅らせれば遅らせるほど、税金の支払いが続くため、早期に売却方針を決定することがコスト削減に直結します。
特定空き家に認定される可能性がある
相続した不動産を放置し、売却までに時間がかかると「特定空き家」に認定される可能性があります。特定空き家とは、倒壊の危険や衛生上の問題があるなど、周囲に悪影響を及ぼす空き家のことです。
認定を受けると、固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が増えます。た、市区町村から修繕や撤去の勧告・命令が出されることもあり、対応を怠れば行政代執行による費用請求のリスクも生じます。
特定空き家に認定されないためにも、不動産を相続した場合は売却に時間をかけないようにしましょう。
相続した不動産を売却する際の6つの注意点

相続不動産を売却する際の注意点は以下6つ挙げられます。
- ①複数の会社に査定を依頼する
- ②単独登記型は贈与とみなされる場合がある
- ③相続した家に住む場合と住まない場合で税金特例が異なる
- ④売却期限の目安は3年以内
- ⑤取得費は親の購入額を引き継ぐ
- ⑥所有期間は親の購入費を引き継ぐ
下記で詳しく解説していくので、後悔が残る売却にならないよう、把握しておきましょう。
①複数の会社に査定を依頼する
相続不動産を売却する際は、適正価格でスムーズに買い手を探して漏れる不動産会社を見つけましょう。
相続不動産には、相続税の納税や特例を使える時期には期限が定められています。期限内にスムーズに売却するためには、売却に慣れた不動産会社に依頼するのがおすすめです。
また、査定をして提示される額は不動産会社によって異なります。そのため、複数の会社に依頼し、査定額や売却活動の内容、スタッフの人柄などを加味して依頼する不動産会社を選びましょう。
②単独登記型は贈与になる場合がある
換価分割という遺産分割方法があります。これは相続財産をお金に監禁し、相続人が分割する方法です。換価分割には、税負担を軽減する効果があります。この換価分割は以下2種類ありまます。
- 共同登記型:複数の相続人で不動産を共有したまま売却する。法定相続に分類
- 単独登記型:不動産を特定の相続人が単独所有し、売却後にそのお金を他の相続人に分配する。遺産分割協議に分類
単独登記型は意思決定をしやすく、所有者本人だけで売却手続きができるのがメリットです。しかし、単独登記型で不動産を売却し、所有者が受け取った現金を他の相続人に分配すると、贈与行為と見なされる恐れがあります。
お金の分配が贈与とみなされないよう対策が必要です。遺産分割協議書に換価分割目的で遺産を取得することを明記しておきましょう。
③相続した家に住む場合と住まない場合で税金特例が異なる
相続した親の家に相続人が住むと利用できる特例が複数あるため、売却時の税金が節税できます。対して、相続した親の家に相続人が住まないと利用できる特例が減るため、売却時の税金を節税しにくいです。
親の家に継いで子が住み、その家を売却する場合はマイホーム売却と同じ扱いです。マイホームの売却は、なるべく税金を発生させない政策的な配慮があるため、利用できる複数の節税特例があります。
一定の要件を満たすと以下5つの特例を利用できます。
- 3,000万円特別控除
- 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換え特例
- 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
対して、相続した親の家に相続人が住まない場合、以下2つの特例が利用できます。
- 取得費加算の特例
- 相続空き家の3,000万円特別控除
このように、利用できる特例が異なるため、どちらに当てはまるのか確認しておきましょう。
④売却期限の目安は3年以内
相続不動産の売却期間は3年以内が目安です。なぜなら、相続不動産で利用できる特例の期限が3年を目安に設定されているからです。
- 取得費加算の特例:相続が開始された日の翌日から3年10カ月以内
- 相続空き家の3,000万円特別控除:相続が開始された日以後、3年を経過する年の12月31日まで
上記の特例の期限は3年を過ぎても間に合います。ただ、不動産の名義変更から引渡しまで半年以上かかるため、3年以内を目安に売却すると安心です。
⑤取得費は親の購入額を引き継ぐ
相続不動産を個人が売却する場合、『譲渡価額ー取得費ー譲渡費用=譲渡所得』で譲渡所得を計算します。
取得費とは、売却不動産を取得した際の購入代金と、維持管理費などを含めた費用です。相続不動産における取得費は、被相続人の購入額を引き継ぎます。
相続不動産を売却する際は、親が不動産を購入した売買契約書から、所得費を明確にすることが必要です。
⑥所有期間は親の購入費を引き継ぐ
相続不動産の所有期間は、親が不動産を購入した日を引き継ぎます。譲渡所得が発生した場合、税金は譲渡所得に税率を課して求めます。
税率は所有期間によって異なり、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年超の場合は長期譲渡所得となります。
所有期間が長いほど税率は低く、節税できる点に注目です。所有期間が5年超の物件を相続したら、相続後すぐに売却しても、長期譲渡所得の税率が適用されます。
相続した不動産の売却を成功させるポイント

相続した不動産の売却を成功させるポイントは以下の3つです。
それぞれのポイントを把握して、相続不動産の売却を成功させましょう。
キレイに清掃する
相続した不動産を売却する際、物件をキレイに清掃しておくことは非常に重要です。第一印象が購入希望者の判断に大きく影響するため、清掃の有無で売却のスピードや価格が左右されるケースがあります。
室内にホコリや汚れが残っていると、築年数以上に古く見えてしまい、マイナスの印象を与える可能性が高いです。特に水回りや窓、床など目に付きやすい箇所は重点的に清掃する必要があります。
また、室内に残置物があると空間が狭く感じられ、生活イメージを持ちにくくなるため、整理整頓や不用品の撤去も効果的です。適切に清掃された物件は、内覧時の印象が良くなり、購入希望者に「すぐに住めそう」「手入れがされている」といった安心感を与えられます。
結果として売却期間の短縮や、希望価格に近い成約にもつながるため、売却活動を始める前の清掃は欠かせない準備のひとつです。
複数の不動産会社に査定を依頼する
査定価格は不動産会社ごとに異なり、一社だけの提示額に依存すると適正な価格が分かりません。複数の査定結果を比較することで、相場を把握しやすくなり、過大評価や過小評価を避けられます。
また、各社の提案内容や対応の質を見比べることで、信頼できる仲介会社を選ぶ判断材料にもできます。売却戦略や販売チャネルについても会社ごとに異なるため、選択肢を広げる意味でも複数査定は有効です。
売却を成功させるには、価格だけでなくサービス内容や実績など総合的な視点で判断する必要があります。
不動産売却の実績が豊富にある会社に依頼する
相続した不動産の売却を成功させるためには、不動産売却の実績が豊富な会社に依頼しましょう。売却に関するノウハウや地域ごとの市場動向を熟知している会社であれば、適正な価格設定や効果的な販売戦略を提案してくれます。
実績が豊富な会社は、査定から契約・引き渡しまでのプロセスをスムーズに進める体制が整っており、トラブルのリスクも低減されます。また、相続不動産特有の税務や法務の相談にも対応できるケースが多く、安心して任せられるのもポイントです。
実績のある会社の場合、類似物件の売却事例に基づいた適切なアドバイスを受けられる点もメリットです。
世田谷区で相続不動産の売却におすすめの不動産会社2選

世田谷区で相続不動産の売却におすすめの不動産会社は以下の2社です。
それぞれの特徴を把握して、自分に適切な不動産会社選びに役立ててみてください。
アドバンスライフ有限会社
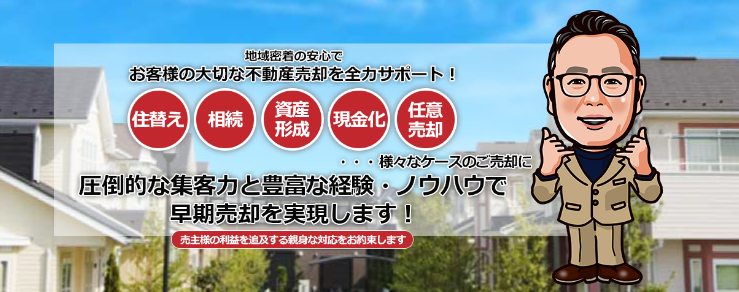
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | アドバンスライフ有限会社 |
| 設立年月日 | 1990年4月6日 |
| 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋1-39-7 ショッピングプラザベルアージュ102 |
| 公式サイト | x |
空き家を売却するなら、アドバンスライフ有限会社がおすすめです。アドバンスライフ有限会社は地域密着型で、不動産の売却に特化している不動産会社です。
圧倒的な集客力と豊富な経験・ノウハウで早期売却をサポートしてくれます。相続不動産の売却も多数手掛けているので、不動産売却が初めての方も安心です。
ホームページでは、不動産相場MAPで、無料相場を簡単にチェックできます。不安な方は、事前に近隣物件の価格を参考にして、価格相場のイメージを掴みましょう。
現在、無料相談・査定を実施しているので、世田谷区でマンション売却を考えている方は参考にしてみてください。
東急リバブル株式会社

東急リバブル株式会社は、世田谷区における相続不動産の売却において高い評価を受けている不動産会社です。豊富な実績と地域に根ざしたネットワークを活かし、複雑な相続案件にも柔軟に対応できるのが特徴です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 東急リバブル株式会社 |
| 設立年月日 | 1972年3月10日 |
| 所在地 | 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-38-7 フォーラム N&N 2階 |
| 公式サイト | https://www.livable.co.jp/ |
特に相続不動産は、所有者の状況や法律的な手続きが複雑になることが多いため、専門的な知識と経験が求められます。東急リバブルは司法書士や税理士と連携し、売却だけでなく相続全体のサポートを提供しているため安心感があります。
また、世田谷区内の市場動向を詳細に分析し、適正な価格設定と効果的な販売戦略を提案してくれるのもポイントです。
また、以下の記事では東急リバブル株式会社の特徴や口コミ、取引事例を紹介していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
まとめ
本記事では、相続不動産の売却に関して、流れや必要な書類、売却する際の注意点などについて解説しました。
相続不動産の売却は状況によって売却の流れや必要書類が変わるため、事前に把握しておくことが大切です。また、上記では、相続不動産の売却で利用できる制度についても紹介しています。利用することで、売却にかかる費用を抑えられるため、確認しておきましょう。
また、最後には世田谷区でマンション売却におすすめの不動産会社を紹介しています。気になる方は、利用を検討してみてください。